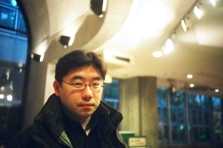2002年度、20代前半の新社会人となって世間にでてくる。新人
の非常識さを憂うのは珍しいことではないけど、今年は特に注
意したほうが良いと思う。
2002年に22才と仮定すると、15才の時は1995年。このころは携
帯電話が値下がりし始め、中高生ですらポケベルから携帯電話
に移行したタイミングなわけだ。
つまり、ガールフレンドやボーイフレンドに電話するときに
本人同士で直接話せる状況だったわけで、僕たちの世代のよう
に、電話にはまず相手の親が出るなんてことはなかったはず。
「夜分失礼します。××と申しますが、○○さんいらっしゃい
ますか?」を経験していない世代。
新人教育担当の方、この点をお忘れ無く。今年の新人、電話の
応対すらできませんよ、きっと。
Saturday, April 27, 2002
Sunday, March 31, 2002
そもそも...
最近、「で、結局何が目的なんだっけ?」と振り出しに立ち戻る議
論や打ち合わせが多い。「何のために」とか「誰のために」といっ
た意識が薄いままに進んでいるプロジェクトの多さに驚く。
何となくわかったつもり、お互いに伝えあっているつもり、こんな
曖昧さが責任の所在を薄くしている。曖昧さを含んだ暗黙知ろか、
あ・うんの呼吸の必要さと便利さはわかっているけど、何事も度が
過ぎるとこじれてしまう。そうなると、正直者というか、物事を
見過ごせない損な性格の持ち主が人身御供となっていく。
「これって結局なんだったっけ?」に立ち戻ることが時には必要で、
仲間内では冗談半分にそもそも理論なんて呼んでいる。
議論が発散して収拾がつかないとき、逆に全員が一方向に押し流さ
れている時の両方で便利なことが多い。
例えば、最近直面した例だけど、「携帯電話から旅行の予約を実現
したい」というテーマがあった。多くのメンバーはwebサイトの設計
はどうしようとか、セキュリティの面で問題がと頭を悩ませていた
けれど、電話受付センターを作ればそれでいいのではないかと落ち
着いた。携帯電話=webアクセスと「思いこんだ」結果、何のためか
を見落とした例だ。ユーザーは旅行の予約をすることが目的であっ
て、手段はどうでもよいわけだ。
単純で明快な答えに限って見落としてしまうものだ。行き詰まったら
「そもそもこれって...」と立ち戻ると、意外と解決するものだ。
論や打ち合わせが多い。「何のために」とか「誰のために」といっ
た意識が薄いままに進んでいるプロジェクトの多さに驚く。
何となくわかったつもり、お互いに伝えあっているつもり、こんな
曖昧さが責任の所在を薄くしている。曖昧さを含んだ暗黙知ろか、
あ・うんの呼吸の必要さと便利さはわかっているけど、何事も度が
過ぎるとこじれてしまう。そうなると、正直者というか、物事を
見過ごせない損な性格の持ち主が人身御供となっていく。
「これって結局なんだったっけ?」に立ち戻ることが時には必要で、
仲間内では冗談半分にそもそも理論なんて呼んでいる。
議論が発散して収拾がつかないとき、逆に全員が一方向に押し流さ
れている時の両方で便利なことが多い。
例えば、最近直面した例だけど、「携帯電話から旅行の予約を実現
したい」というテーマがあった。多くのメンバーはwebサイトの設計
はどうしようとか、セキュリティの面で問題がと頭を悩ませていた
けれど、電話受付センターを作ればそれでいいのではないかと落ち
着いた。携帯電話=webアクセスと「思いこんだ」結果、何のためか
を見落とした例だ。ユーザーは旅行の予約をすることが目的であっ
て、手段はどうでもよいわけだ。
単純で明快な答えに限って見落としてしまうものだ。行き詰まったら
「そもそもこれって...」と立ち戻ると、意外と解決するものだ。
Saturday, March 30, 2002
No more戦略論者
一応MBAの学生なので、戦略論を語ることが当たり前の環境に晒
されている。何事においても、「まず戦略ありきでしょ」とか、
「戦略の欠如を戦術では補えないね」とか歯の浮くような台詞を
もっともらしく口にしてしまう。
個人的には、戦略論などというたかだか30年程度の歴史しかもた
ない学問に興味はない。学問や理論と呼べるものではなく、例外
の寄せ集めというか、後付の解説に過ぎないと思っている。
というのも、ポーターやバーニー、アーカーなどこの業界で幅を
きかせている人間が言っていることは、とうの昔に言われている。
僕は、カタカナで説明するより、熟語や故事成語で説明するよう
に心がけている。
例えば、トレードオフ。これは「二兎を追うもの一兎をもえず」
のことだ。アジリティは「疾きこと風のごとし」、5forcesは
「彼を知りて己を知れば百戦あやうからず」、ベンチマークや
ベストプラクティスは「人の振り見て我が振り直せ」。交渉の
BATNAは最善策、次善策のこと。
こんな風に、皆が一度は耳にしたことがある言葉で説明した方
が誤解を招かずに良いと思う。
カタカナで惑わし、本来の意味を見失っている戦略論者はもう
いらない。
されている。何事においても、「まず戦略ありきでしょ」とか、
「戦略の欠如を戦術では補えないね」とか歯の浮くような台詞を
もっともらしく口にしてしまう。
個人的には、戦略論などというたかだか30年程度の歴史しかもた
ない学問に興味はない。学問や理論と呼べるものではなく、例外
の寄せ集めというか、後付の解説に過ぎないと思っている。
というのも、ポーターやバーニー、アーカーなどこの業界で幅を
きかせている人間が言っていることは、とうの昔に言われている。
僕は、カタカナで説明するより、熟語や故事成語で説明するよう
に心がけている。
例えば、トレードオフ。これは「二兎を追うもの一兎をもえず」
のことだ。アジリティは「疾きこと風のごとし」、5forcesは
「彼を知りて己を知れば百戦あやうからず」、ベンチマークや
ベストプラクティスは「人の振り見て我が振り直せ」。交渉の
BATNAは最善策、次善策のこと。
こんな風に、皆が一度は耳にしたことがある言葉で説明した方
が誤解を招かずに良いと思う。
カタカナで惑わし、本来の意味を見失っている戦略論者はもう
いらない。
Thursday, December 13, 2001
名前
ちょっと前のニュースだけど、子供が誘拐されて無事に保護された
事件があった。で、その子供の名前が「騎士」と書いて「ナイト」
君だった。
おそらくこのナイト君の両親は「外国の人も発音できるように」と
考えて命名したのだと思う。このコンセプト自体はけっこう古くか
らあると思うし、良いことだと思う。先月、友人のアメリカ人男性
に子供が生まれた。奥さんは日本人だからその子供は将来にわたっ
てアメリカと日本の両方にが生活の場となると思う。カレンと名付
けたのだけど、理由は日本人もアメリカ人も発音できて両方の国で
通用する名前だからとのこと。
この「通用する」ということが大切なのだと思う。カレンという響
きは、日本語では「可憐」から連想される意味を持つし、アメリカ
では名前として使われているのだから、何かしらのイメージはある
のだろう。日本人に外国風の名前をつけるのではなく、「通用する」
名前をつけることが大事なのでは?とナイト君の両親に問いたい。
だいたい、騎士と書いてナイトでは、日本語としてなんの意味も持
たないではないか。さらに言ってみば、外国人の前で自己紹介の時
に、仮に名字を田中としよう、「Hi, I am Naito Tanaka」ってのは
どーよ。逆に外国人から怪しがられるぞ、きっと。
それぞれの国には、それぞれの国らしい名前がある。外国の名前を
つけることと、外国でも憶えてもらえる名前は全く似て非なるもの
ではないでしょうか。
さて、田中騎士君、アルファベットで名前を書くとき、あなたは
「Naito Tanaka」ですか、それとも「Knight Tanaka」ですか?
*注
人名についての私的な意見を述べたまでであり、僕が不可解に
思う一例として「騎士」を取り上げました。ナイト君本人と
その両親を誹謗中傷する目的ではありませんので、その点は
ご理解ください。
事件があった。で、その子供の名前が「騎士」と書いて「ナイト」
君だった。
おそらくこのナイト君の両親は「外国の人も発音できるように」と
考えて命名したのだと思う。このコンセプト自体はけっこう古くか
らあると思うし、良いことだと思う。先月、友人のアメリカ人男性
に子供が生まれた。奥さんは日本人だからその子供は将来にわたっ
てアメリカと日本の両方にが生活の場となると思う。カレンと名付
けたのだけど、理由は日本人もアメリカ人も発音できて両方の国で
通用する名前だからとのこと。
この「通用する」ということが大切なのだと思う。カレンという響
きは、日本語では「可憐」から連想される意味を持つし、アメリカ
では名前として使われているのだから、何かしらのイメージはある
のだろう。日本人に外国風の名前をつけるのではなく、「通用する」
名前をつけることが大事なのでは?とナイト君の両親に問いたい。
だいたい、騎士と書いてナイトでは、日本語としてなんの意味も持
たないではないか。さらに言ってみば、外国人の前で自己紹介の時
に、仮に名字を田中としよう、「Hi, I am Naito Tanaka」ってのは
どーよ。逆に外国人から怪しがられるぞ、きっと。
それぞれの国には、それぞれの国らしい名前がある。外国の名前を
つけることと、外国でも憶えてもらえる名前は全く似て非なるもの
ではないでしょうか。
さて、田中騎士君、アルファベットで名前を書くとき、あなたは
「Naito Tanaka」ですか、それとも「Knight Tanaka」ですか?
*注
人名についての私的な意見を述べたまでであり、僕が不可解に
思う一例として「騎士」を取り上げました。ナイト君本人と
その両親を誹謗中傷する目的ではありませんので、その点は
ご理解ください。
Tuesday, November 27, 2001
no more 携帯のリコール
おそらく、ほとんどの人が予想していたであろうことが起き
てしまった。新しい携帯電話の機種が発売されると、決まっ
てリコール騒ぎが起きることは、もはや毎度のことである。
しかも不思議なことに、ある特定の携帯電話事業社でセけ
起きるのだ。
その会社の、2001年11月26日付けのリリースによると、
「ある条件下で作成された一部サイトに接続した際、フリー
ズしてデータが削除されます」との発表が成されている。こ
の「ある条件下」について、CNET等のニュースサイトが詳細
に報じているが、どうやら「大容量のデータを分割して受信
するサイト」のことらしい。普通に解説すれば、「ファイル
サイズや送信量の大きいデータ、つまり音声や映像等を配信
するサイト」である。これはまさに第3世代携帯電話が売り文
句にしているサイトではないか。
巨額の開発投資、宣伝広告費を投入したサービスで今回のリ
コール騒ぎが発生したことは、もはや同情に値する。
また、リコール騒ぎが起きるたびに、原因を「ソフトウェア
のバグ」と決めつけている。なぜこうも度々ソフトウェアの
バグが残った状態で製品が発売されるのだろうか。
ソフトウェアの開発は、通常、要件定義、設計、開発、テスト
のサイクルで開発される。この中でも、要件定義とテストが
最も重要な作業に当たる。どんな機能を実現するソフトウェ
アを作るかを「定義」し、それが確実に動作することを「テ
スト」するのである。
ところが、携帯電話産業におけるソフトウェア開発は、この2
点、「要件定義」と「テスト」がお粗末だと聞く。
というのも、要件が五月雨式に発案され、いつまでも仕様が固
まらず、しかし開発スケジュールや予算は決まっているので、
とりあえず設計や開発に着手せざるを得ず、開発中にも新規の
要件が追加され設計・開発期間が延長され、結果としてテスト
期間が短縮・省略されてしまうのだ。
多くのアイデアがいくつも湧きだし、要件として追加されるこ
とは決して間違いではない。ただ、要件がダラダラと設計・開
発に組み込まれていくことが問題であり、これはプロジェクト
管理能力の欠落といわざるを得ない。
また、そもそも開発期間が、「市場の急速な変化に対応する」と
の大義名分のもとにタイトな設定になっている点も見逃せない。
これで何人の開発担当者がバーンアウトしていることか。
さらに、ここ数年、ソフトウェアにバグが存在することを肯定す
るような風潮もある。「3回程度のメジャーバージョンアップが
なされないと使い物にならない」とか「複雑なロジックで成り立
つソフトウェアに100%を求めてはいけない」などなど。
これは全く論外な意見だと思う。家電や自動車さえ機器の中に
コンピュータを搭載し、OSやアプリケーションが稼働している。
一度事故が起これば、人命に関わるだけに、家電や自動車の品質
管理能力は非常に高い。一方、パソコンや携帯電話等の機器は万
が一事故が起こったとしても、人命に関わる危険性は低いため、
品質管理がないがしろにされる傾向が強い。
早期の市場投入による成功者利益、バージョンアップでの買い替え
需要での儲ける仕組みなど、企業にはいろいろな事情があるにせよ、
せめて最低限の品質が保証され、確実に使い物になる製品やサービ
スを望むことは消費者のエゴなのだろうか。
大々的な宣伝をし、鳴り物入りで投入された製品やサービスであれ
ば、消費者サイドの期待感は高まる。この期待感にはこたえてもら
いたいものだ。
てしまった。新しい携帯電話の機種が発売されると、決まっ
てリコール騒ぎが起きることは、もはや毎度のことである。
しかも不思議なことに、ある特定の携帯電話事業社でセけ
起きるのだ。
その会社の、2001年11月26日付けのリリースによると、
「ある条件下で作成された一部サイトに接続した際、フリー
ズしてデータが削除されます」との発表が成されている。こ
の「ある条件下」について、CNET等のニュースサイトが詳細
に報じているが、どうやら「大容量のデータを分割して受信
するサイト」のことらしい。普通に解説すれば、「ファイル
サイズや送信量の大きいデータ、つまり音声や映像等を配信
するサイト」である。これはまさに第3世代携帯電話が売り文
句にしているサイトではないか。
巨額の開発投資、宣伝広告費を投入したサービスで今回のリ
コール騒ぎが発生したことは、もはや同情に値する。
また、リコール騒ぎが起きるたびに、原因を「ソフトウェア
のバグ」と決めつけている。なぜこうも度々ソフトウェアの
バグが残った状態で製品が発売されるのだろうか。
ソフトウェアの開発は、通常、要件定義、設計、開発、テスト
のサイクルで開発される。この中でも、要件定義とテストが
最も重要な作業に当たる。どんな機能を実現するソフトウェ
アを作るかを「定義」し、それが確実に動作することを「テ
スト」するのである。
ところが、携帯電話産業におけるソフトウェア開発は、この2
点、「要件定義」と「テスト」がお粗末だと聞く。
というのも、要件が五月雨式に発案され、いつまでも仕様が固
まらず、しかし開発スケジュールや予算は決まっているので、
とりあえず設計や開発に着手せざるを得ず、開発中にも新規の
要件が追加され設計・開発期間が延長され、結果としてテスト
期間が短縮・省略されてしまうのだ。
多くのアイデアがいくつも湧きだし、要件として追加されるこ
とは決して間違いではない。ただ、要件がダラダラと設計・開
発に組み込まれていくことが問題であり、これはプロジェクト
管理能力の欠落といわざるを得ない。
また、そもそも開発期間が、「市場の急速な変化に対応する」と
の大義名分のもとにタイトな設定になっている点も見逃せない。
これで何人の開発担当者がバーンアウトしていることか。
さらに、ここ数年、ソフトウェアにバグが存在することを肯定す
るような風潮もある。「3回程度のメジャーバージョンアップが
なされないと使い物にならない」とか「複雑なロジックで成り立
つソフトウェアに100%を求めてはいけない」などなど。
これは全く論外な意見だと思う。家電や自動車さえ機器の中に
コンピュータを搭載し、OSやアプリケーションが稼働している。
一度事故が起これば、人命に関わるだけに、家電や自動車の品質
管理能力は非常に高い。一方、パソコンや携帯電話等の機器は万
が一事故が起こったとしても、人命に関わる危険性は低いため、
品質管理がないがしろにされる傾向が強い。
早期の市場投入による成功者利益、バージョンアップでの買い替え
需要での儲ける仕組みなど、企業にはいろいろな事情があるにせよ、
せめて最低限の品質が保証され、確実に使い物になる製品やサービ
スを望むことは消費者のエゴなのだろうか。
大々的な宣伝をし、鳴り物入りで投入された製品やサービスであれ
ば、消費者サイドの期待感は高まる。この期待感にはこたえてもら
いたいものだ。
Sunday, November 25, 2001
二足の草鞋
経営と技術の両方を知っている人材だとか、戦略と実務の両方を
語れる人材が必要ということは、もう何年も言われている。僕が
社会人になったらも良く聞くし、何十年も前に書かれた本にも度々
登場する。
こうも長くの間「必要だ」と言われ続けているのはなんでだろう。
そのニーズを満たす人がいないのだろうか。
そんなことはない。実際、複数の専門領域を持つ知り合いが何人
かいる。天才的なプログラマでありながら会計士だったり、グ
ロービスに通う医学生、文学部出身のコンサルタント、生物学修
士の新聞記者...。こういう僕自身も、複数の専門領域を持って
いる。
では、他に理由があるのではないか。僕は2つの理由があると思う。
まず一つ目、二足の草鞋を履く人がいないのではなく、そういった
人が活躍できる組織や職種が少ないことが一番の理由だと思う。
社会では、何か一つの職業を選ぶ必要がある。そしてそれは往々に
して、特定の職務や専門性を求められることが多いわけだ。経営規
模の大小を問わず、組織という物は概して縦割りだ。柔軟性があっ
て、オーバーラップしている組織もあるが、それぞれの組織は明確
な責任範囲があるという点において、とても閉じた状況に置かれて
いる。
二つ目の理由は、技術者の地位が低いこと。
技術を語る経営者は求められるが、経営を語る技術者は煙たがられる
ことが多い。コンサルティングの仕事を通じて知り合った会社の多く
は、そんな社風を持っていた。製造業や研究開発が基幹業務の会社で
あっても、営業、マーケティング、経営企画、財務等の部署がいわゆ
る出世街道なわけだ。
そして、それらの部署にいる人が技術に詳しくないことは許されるが、
研究者や技術者が財務諸表を読めないと馬鹿にされる。
そういえば、二足の草鞋って言葉は、良い意味だけではないし、二兎
を追うもの一兎をも得ずともいう。
果たして、複数の専門領域を持つ人材、俗に言うπ型人間というのは
本当に求められているのだろうか。
語れる人材が必要ということは、もう何年も言われている。僕が
社会人になったらも良く聞くし、何十年も前に書かれた本にも度々
登場する。
こうも長くの間「必要だ」と言われ続けているのはなんでだろう。
そのニーズを満たす人がいないのだろうか。
そんなことはない。実際、複数の専門領域を持つ知り合いが何人
かいる。天才的なプログラマでありながら会計士だったり、グ
ロービスに通う医学生、文学部出身のコンサルタント、生物学修
士の新聞記者...。こういう僕自身も、複数の専門領域を持って
いる。
では、他に理由があるのではないか。僕は2つの理由があると思う。
まず一つ目、二足の草鞋を履く人がいないのではなく、そういった
人が活躍できる組織や職種が少ないことが一番の理由だと思う。
社会では、何か一つの職業を選ぶ必要がある。そしてそれは往々に
して、特定の職務や専門性を求められることが多いわけだ。経営規
模の大小を問わず、組織という物は概して縦割りだ。柔軟性があっ
て、オーバーラップしている組織もあるが、それぞれの組織は明確
な責任範囲があるという点において、とても閉じた状況に置かれて
いる。
二つ目の理由は、技術者の地位が低いこと。
技術を語る経営者は求められるが、経営を語る技術者は煙たがられる
ことが多い。コンサルティングの仕事を通じて知り合った会社の多く
は、そんな社風を持っていた。製造業や研究開発が基幹業務の会社で
あっても、営業、マーケティング、経営企画、財務等の部署がいわゆ
る出世街道なわけだ。
そして、それらの部署にいる人が技術に詳しくないことは許されるが、
研究者や技術者が財務諸表を読めないと馬鹿にされる。
そういえば、二足の草鞋って言葉は、良い意味だけではないし、二兎
を追うもの一兎をも得ずともいう。
果たして、複数の専門領域を持つ人材、俗に言うπ型人間というのは
本当に求められているのだろうか。
Wednesday, November 14, 2001
似たもの同士
友達とか知り合いってのは、どこか自分に似ていたり、共
通の趣味があったりするものだ。そもそも、知り合うきっ
かけが趣味や興味を基にしていることが多いわけだから、
当然といえば当然かも知れない。
しかも、学校、バイト、就職とかっていうのは、偏差値、
年齢、居住地域とかで輪切りにされて、とかく均質な人間
が集まりやすい構造になっている。似た価値観、考え方、
育ち、趣味・興味とか。
日本はモノカルチャーだし、ほぼ単一民族だという文化的
背景も影響していると思う。
「縁」とえ「巡り合わせ」ってのは、こんな輪切りの構造
に多少なりとも左右されているのかもしれない。
ところが、なんだけど。輪切りでありつつも、例えば、僕
の印象というのは、学生時代の同級生、lomoのメンバー、
会社の同期、家族とかで違っていると思う。それぞれの場
の中では、僕は違う人間として認識されていると思う。
学校の同級生は学校での僕をよく知っているだろうけど、
家の中での僕や、バイト先での僕はよく知らないはず。
友達や知り合いの意外な一面を知ったときの意外さは新鮮
な驚きだったりする。
似たもの同士でありながらも、意外さと多様性は常に持っ
ていたいものだ。同じような価値観や話題に終始する人と
は長くつき合えないと思う。きっと飽きてしまう(そもそ
も僕は、ベッタリとした人間関係は好きじゃない)。
多様性はパワーなのだと、つくづく思う。類似性と多様性
のバランスが気さくな間柄を保つ秘訣だと思う。
/**おまけ**/
最近のマーケティング手法は、類似性だけで市場や顧客を
捉えることが多い。「セグメンテーション」を盲信しすぎ
ているように思う。セグメンテーション自体は有用な手法
だし、僕もよく使う。けど、市場や顧客を分類する軸とい
か、視点はもっと多様だと思う。企業が定量化できる消費
額や来店頻度、商品認知度などの指標では、顧客や市場の
ごく限られた部分しか捉えられないはずだ。
ではどうするか、論文執筆中です。
通の趣味があったりするものだ。そもそも、知り合うきっ
かけが趣味や興味を基にしていることが多いわけだから、
当然といえば当然かも知れない。
しかも、学校、バイト、就職とかっていうのは、偏差値、
年齢、居住地域とかで輪切りにされて、とかく均質な人間
が集まりやすい構造になっている。似た価値観、考え方、
育ち、趣味・興味とか。
日本はモノカルチャーだし、ほぼ単一民族だという文化的
背景も影響していると思う。
「縁」とえ「巡り合わせ」ってのは、こんな輪切りの構造
に多少なりとも左右されているのかもしれない。
ところが、なんだけど。輪切りでありつつも、例えば、僕
の印象というのは、学生時代の同級生、lomoのメンバー、
会社の同期、家族とかで違っていると思う。それぞれの場
の中では、僕は違う人間として認識されていると思う。
学校の同級生は学校での僕をよく知っているだろうけど、
家の中での僕や、バイト先での僕はよく知らないはず。
友達や知り合いの意外な一面を知ったときの意外さは新鮮
な驚きだったりする。
似たもの同士でありながらも、意外さと多様性は常に持っ
ていたいものだ。同じような価値観や話題に終始する人と
は長くつき合えないと思う。きっと飽きてしまう(そもそ
も僕は、ベッタリとした人間関係は好きじゃない)。
多様性はパワーなのだと、つくづく思う。類似性と多様性
のバランスが気さくな間柄を保つ秘訣だと思う。
/**おまけ**/
最近のマーケティング手法は、類似性だけで市場や顧客を
捉えることが多い。「セグメンテーション」を盲信しすぎ
ているように思う。セグメンテーション自体は有用な手法
だし、僕もよく使う。けど、市場や顧客を分類する軸とい
か、視点はもっと多様だと思う。企業が定量化できる消費
額や来店頻度、商品認知度などの指標では、顧客や市場の
ごく限られた部分しか捉えられないはずだ。
ではどうするか、論文執筆中です。
Subscribe to:
Posts (Atom)