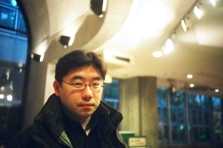スイスの高級時計、「フランクミューラー」。創業は1992年だったのか。
知らなかった。スイスの高級時計って聞くと、条件反射的に18世紀ごろから続いているような気になってしまう。
思い込みってこわいな。
Saturday, March 24, 2007
Wednesday, March 21, 2007
ゆとり教育と段取り
日経BP社のwebサイトで連載中の「立花隆の「メディア ソシオ-ポリティクス」の第101回、2007年3月16日のエントリーにて、日本人の知力崩壊について書かれていた。
ふむふむと納得できることが書かれていて、とりわけ、「今年から、大学には、「ゆとり教育100%」つまり、学校に入ってから全過程ゆとり教育でやってきましたという連中が入ってくるようになって、大学の先生方をとまどわせている。」、そして「彼らが大学を出て一般社会に出ていくのはあと4年後のことになる。」との記述にゾッとした。
このブログ、2002年4/27のエントリで「今年の新入社員にご用心」http://seiron.blogspot.com/2002/04/blog-post.htmlと書いた。携帯電話世代は電話の応対すらろくにできないかもと書いたのだが、今回の立花氏の記述が持つインパクトはその比ではない。ゆとり教育でまっさきに削減された科目は理数系の科目だった。理数系の科目を選考することは、なにも量子物理学や高等抽象数学の研究者を育成することにはつながらない。「複雑そうに見えるものごとを細かく分解して、単純なものの集合体として理解する」ための頭の使い方が理数系科目の履修で身につく。これは僕自身の経験上確かだと思う。
構造化、クリティカル・ロジカルシンキングといった言葉が飛び交う業界、たとえばコンサルティング、証券会社のエコノミスト、法曹界で理科系バックグラウンドを持つものが活躍している背景には、こういった理由がある。構造化とか書くと堅苦しいが、要は「手戻りをなくす段取り上手」になるための頭の使い方のことだ。
そう考えると、数年後には段取りが苦手で、何度も手直しや手戻りを発生させてしまう「不器用な人々」が新入社員としてやってくるのだろうか。高倉健よろしく「不器用ですから」ですむ問題ではなさそうだ。
そのとき、僕はいったいどうなるだろう。細かく口うるさい、型にはまった仕事の進め方しかしない、段取上手ではなく社内政治家、いかにも管理職だよね、などと揶揄されるのだろうか。あるいはその時の風潮にあわせて「場面でよくね?」といった場当たり的な人間になるのだろうか。
そんな数年後は、数年後に必ずやってくる。
ふむふむと納得できることが書かれていて、とりわけ、「今年から、大学には、「ゆとり教育100%」つまり、学校に入ってから全過程ゆとり教育でやってきましたという連中が入ってくるようになって、大学の先生方をとまどわせている。」、そして「彼らが大学を出て一般社会に出ていくのはあと4年後のことになる。」との記述にゾッとした。
このブログ、2002年4/27のエントリで「今年の新入社員にご用心」http://seiron.blogspot.com/2002/04/blog-post.htmlと書いた。携帯電話世代は電話の応対すらろくにできないかもと書いたのだが、今回の立花氏の記述が持つインパクトはその比ではない。ゆとり教育でまっさきに削減された科目は理数系の科目だった。理数系の科目を選考することは、なにも量子物理学や高等抽象数学の研究者を育成することにはつながらない。「複雑そうに見えるものごとを細かく分解して、単純なものの集合体として理解する」ための頭の使い方が理数系科目の履修で身につく。これは僕自身の経験上確かだと思う。
構造化、クリティカル・ロジカルシンキングといった言葉が飛び交う業界、たとえばコンサルティング、証券会社のエコノミスト、法曹界で理科系バックグラウンドを持つものが活躍している背景には、こういった理由がある。構造化とか書くと堅苦しいが、要は「手戻りをなくす段取り上手」になるための頭の使い方のことだ。
そう考えると、数年後には段取りが苦手で、何度も手直しや手戻りを発生させてしまう「不器用な人々」が新入社員としてやってくるのだろうか。高倉健よろしく「不器用ですから」ですむ問題ではなさそうだ。
そのとき、僕はいったいどうなるだろう。細かく口うるさい、型にはまった仕事の進め方しかしない、段取上手ではなく社内政治家、いかにも管理職だよね、などと揶揄されるのだろうか。あるいはその時の風潮にあわせて「場面でよくね?」といった場当たり的な人間になるのだろうか。
そんな数年後は、数年後に必ずやってくる。
Tuesday, February 27, 2007
ソフトとハード
いささか旧聞だが、2007年2/9の日経MJの記事で、「ハードでなくソフト」について書かれていた。SONYでの製品開発がハード重視からソフト重視に移行していることについての記事だった。社内では「ソフトの言葉で語れ」などと喝破されることも多いそうだ。
さて、僕が高校生のころ、今から20年ほどまえのことだろうか、同じように「ソフト」という言葉がはやったことがある。コンピューターの登場でハードウェア、ソフトウェアとの言葉が広まったころだ。さらに当時はCIの名の下に、アイデンティティ構築のためのイメージ訴求が大流行だった。製品名を出さずに「心象風景」的な映像を使うCM、耳障りの良いキャッチコピーはその最たる例だ。パルコのCMや糸井重里に代表される。
家でテレビを見ていたときにホンダのCMが流れた。車のエクステリアに、談笑しながら歩く女性グループの絵が重なるカットだ。それを見ていた親が、「ソフトで売ろうとしているなぁ。車と関係ない女性の映像をかぶせてくるなんて」と言っていたことは今でも覚えている。
記事で「ハードとソフト」と見かけたとき、高校生のころを思い出した。それと同時に、企業が打てる打ち手って変わらないんだなぁとの思いが改めて強くなった。
さて、僕が高校生のころ、今から20年ほどまえのことだろうか、同じように「ソフト」という言葉がはやったことがある。コンピューターの登場でハードウェア、ソフトウェアとの言葉が広まったころだ。さらに当時はCIの名の下に、アイデンティティ構築のためのイメージ訴求が大流行だった。製品名を出さずに「心象風景」的な映像を使うCM、耳障りの良いキャッチコピーはその最たる例だ。パルコのCMや糸井重里に代表される。
家でテレビを見ていたときにホンダのCMが流れた。車のエクステリアに、談笑しながら歩く女性グループの絵が重なるカットだ。それを見ていた親が、「ソフトで売ろうとしているなぁ。車と関係ない女性の映像をかぶせてくるなんて」と言っていたことは今でも覚えている。
記事で「ハードとソフト」と見かけたとき、高校生のころを思い出した。それと同時に、企業が打てる打ち手って変わらないんだなぁとの思いが改めて強くなった。
Sunday, February 25, 2007
ボーダレス、ユニバーサル
酒とタバコとお茶は世界中にあるね。酒飲んであばれて、煙が目にしみたって言って泣いたり、煙を吐きながらため息ついたり、気持ちを落ち着けるときには暖かいお茶。
世界中どこにでもある風景。なんだか不思議だ。
世界中どこにでもある風景。なんだか不思議だ。
Tuesday, February 20, 2007
セカンドライフと動物の森
セカンドライフ(http://secondlife.com/)をはじめてみた。なにやら「流行っていそう」とのことで、まったくの興味本位。
まだ深くやりこんでいないので何が魅力なのかはユーザーとしては実感できないけど、広告代理店とか斡旋業者、ネットワークビジネス関係者がこぞって盛り上げようとしている理由はわかった。
セカンドライフでは、リンデンドルという仮想通貨が登場する。それを原資としてさまざまな活動をし、しかもそれがクレジットカードを介して実際の通貨と兌換性がある。
これまではネットを新しいチャネルと認識して、広告枠を買うことで代理店が関わってきたけど、ここに通貨の概念が加わることでプロモーションの可能性がでてくるわけだ。セカンドライフ内でのイベント企画や広告活動、参加者の組織化で、現実世界よろしく手数料商売やネットワーク販売ができるようになると目論んでいるはず。
僕はセカンドライフに違和感を感じる。アバターの見かけや3Dアニメが日本人離れしているからかもしれないが、なによりも現実とネット(ゲーム)を一体化させようとすることがなじめない。動物の森のように、果物や魚を採って家具をそろえたりする方がよっぽど感情移入できて楽しめるのは僕の気のせいか?
まだ深くやりこんでいないので何が魅力なのかはユーザーとしては実感できないけど、広告代理店とか斡旋業者、ネットワークビジネス関係者がこぞって盛り上げようとしている理由はわかった。
セカンドライフでは、リンデンドルという仮想通貨が登場する。それを原資としてさまざまな活動をし、しかもそれがクレジットカードを介して実際の通貨と兌換性がある。
これまではネットを新しいチャネルと認識して、広告枠を買うことで代理店が関わってきたけど、ここに通貨の概念が加わることでプロモーションの可能性がでてくるわけだ。セカンドライフ内でのイベント企画や広告活動、参加者の組織化で、現実世界よろしく手数料商売やネットワーク販売ができるようになると目論んでいるはず。
僕はセカンドライフに違和感を感じる。アバターの見かけや3Dアニメが日本人離れしているからかもしれないが、なによりも現実とネット(ゲーム)を一体化させようとすることがなじめない。動物の森のように、果物や魚を採って家具をそろえたりする方がよっぽど感情移入できて楽しめるのは僕の気のせいか?
Monday, February 19, 2007
キャッチコピー
ここ最近見かけた似たようなパターンのキャッチコピー。韻を踏んでいるようで踏んでいないのが気持ち悪い。
ココロ、カラダ、きれい:LOHAS系のイベント
ココロ、カラダ、みなぎる:レッドブル(だと思う)の新コピー)
キブン、ジブン、たかぶる:タバコ
少し前に良く見かけたパターンが、
○○、はじまる
○○、ひろまる
の「名詞+動詞」系。
言い回しや構成にも流行があるんだろうけど、似たようなこと言われても差別化されないじゃん。ま、制作サイドからすれば、個別の製品なんて興味が無く、「あのコピーもこのコピーも弊社のクリエが担当しました....」って言いたいわけだから、似かよってもいいのか。
ココロ、カラダ、きれい:LOHAS系のイベント
ココロ、カラダ、みなぎる:レッドブル(だと思う)の新コピー)
キブン、ジブン、たかぶる:タバコ
少し前に良く見かけたパターンが、
○○、はじまる
○○、ひろまる
の「名詞+動詞」系。
言い回しや構成にも流行があるんだろうけど、似たようなこと言われても差別化されないじゃん。ま、制作サイドからすれば、個別の製品なんて興味が無く、「あのコピーもこのコピーも弊社のクリエが担当しました....」って言いたいわけだから、似かよってもいいのか。
Thursday, February 15, 2007
プチ同窓会
MBAの時の同級生、米空軍のパイロットが日本に来ると連絡があったのは一昨日のこと。急な知らせだったので新宿で5人でのひっそりとした同期会。
当時は空軍のパイロットだった彼も、今ではペンタゴン勤務日本担当司令官。中佐だ。「佐」がつく役職なんて、シャァしか知らないよ....。
そんな役職の彼が来日するのだから、政策上の用事に違いない。
集まった他のメンバーもそれなりのもので、仕事、国、政策、政治、家族、プライベートと多岐にわたる会話で盛り上がる。
僕達が集まるときの店は、歌舞伎町にあるカウンターだけの小料理屋だ。80になる女将さんが切り盛りしているその店は、55年の歴史がある。僕達はいつも女将さんが出してくれる糠漬けやおから、山芋の千切り等々を肴にお酒を飲むんだ。今日は蕗がおいしかった。
僕達がもう何年かして次のステップやステージに進んだとき、こうして集まれる場所があるといいな。願わくば、この店で会えるといいなと思ったんだ。
当時は空軍のパイロットだった彼も、今ではペンタゴン勤務日本担当司令官。中佐だ。「佐」がつく役職なんて、シャァしか知らないよ....。
そんな役職の彼が来日するのだから、政策上の用事に違いない。
集まった他のメンバーもそれなりのもので、仕事、国、政策、政治、家族、プライベートと多岐にわたる会話で盛り上がる。
僕達が集まるときの店は、歌舞伎町にあるカウンターだけの小料理屋だ。80になる女将さんが切り盛りしているその店は、55年の歴史がある。僕達はいつも女将さんが出してくれる糠漬けやおから、山芋の千切り等々を肴にお酒を飲むんだ。今日は蕗がおいしかった。
僕達がもう何年かして次のステップやステージに進んだとき、こうして集まれる場所があるといいな。願わくば、この店で会えるといいなと思ったんだ。
Subscribe to:
Posts (Atom)